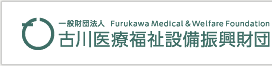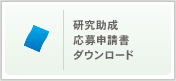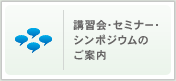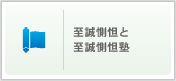2019/07/08
古川医療福祉設備振興財団第5回研究助成による研究報告書 講評
※敬称略 役職等は研究助成申請時のもの
■ 研究助成金対象者
新潟医療福祉大学 健康科学部健康スポーツ学科 准教授 佐藤 大輔
■ 研究課題名
「浸水が大脳基底核のコリン作動系に及ぼす影響の解明とニューロモデュレーションへの応用」
脳内コリン作動性ニューロンはその機能低下が認知障害を伴う神経変性疾患の特徴の一つとして知られており、認知症などの理学的治療や治療薬開発のターゲットとして知られている。本研究は脳内の神経伝達物質の動態をNMR-Spectroscopy(MRS)で検討したもので、健常者を対象とし、(1)主に大脳基底核のコリン作動系の評価が非侵襲的刺激下に可能であることを示唆するとともに、(2)体の浸水という刺激でどう変化するかを検討している。後者は、幾つかの浸水試験の中で35度での腋窩浸水がコリン作動系を変化させるとしている。これらの成果は認知機能改善への非侵襲的刺激法の開発に寄与する可能性があると思われる。なお、健常人が対象であり、結果の分析においてもまだ確たる成果とは言い難く、(2)についても予備的結果の域を出ていないと思われる。また、高齢者の認知症患者で浸水試験(冷水)が果たして非侵襲的な治療なのか疑問が残り、次のステップでの成果が待たれる。
■ 研究助成金対象者
新潟医療福祉大学 医療技術学部理学療法学科 講師 正木 光裕
■ 研究課題名
「脳性麻痺児の日常生活動作、認知の発達と関連する上肢筋の筋量および筋内非収縮組織の解明」
脳性麻痺児が日常動作で使う上肢筋の筋量、筋内非収縮組織と認知機能の発達の相関関係を明らかにしていくというユニークな発想の研究で、調査対象者には新潟県立東新潟特別支援学校の協力を得て同校所属の脳性麻痺児計29名をあて、研究者の調査項目「報告書のB.研究方法の測定項目・方法の①~⑨」の順で測定を実施し、a:測定データをShapiro-Wilkの正規性検定で b:測定値の適正を確認の上、本題である「日常動作で使う上肢の筋肉筋量、筋内非収縮組織」については超音波診断装置などを使用し c:筋厚、筋輝度を測定。「認知機能の発達」は、d:WISC-Ⅳ(ウィスク・フォー)知能検査を用いて臨床心理士が評価するステップでまとめを行い、その相関には e:有意な関連が見られ、脳性麻痺児において上肢を使用した日常生活動作、認知機能には上肢筋の筋量が関連することが示唆された。と結論付けている。
本研究成果は、特別支援学校・学級などといった教育実践の現場で脳性麻痺児に関わっている学校教諭やリハビリテーションスタッフが、運動トレーニングを選択する際の指針となると考えられる、また、脳性麻痺児の上肢を使用した日常生活動作の発達、認知の発達を促す効果的な運動プログラムの開発に向けた研究の実施に、今後つながる可能性があるとも言及している。
ただ、研究テーマ、着眼点がユニークなものであるがゆえに、動作量、超音波診断装置での結果、検定グラフ、評価など重要な測定や検定結果の数値を示し、上肢筋肉を使う日常生活動作と認知機能に筋量が関連すると導いた結論の根拠として示されたい。それらを含めて、今後のさらなる進展を期待するものである。
■ 研究助成金対象者
首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 建築学域 博士後期課程 石田(阿部) 光
■ 研究課題名
「精神疾患患者の通所施設における生活環境整備に関する研究」
精神保健医療福祉領域の制度改革が進められている中で「入院医療から地域生活中心へ」社会復帰施設と病院との連携体制を構築することが求められている。その中で、患者の精神状態や疾病の特性に応じて施設内の生活環境を整え、改善し、患者の社会復帰支援に対する具体的な動きが求められる。
この研究では、初年度にアンケート調査、施設図面収集ならびに訪問調査のための施設への協力依頼を終えている。その上で、今回は対象を26施設から10施設に絞りアンケート調査を行い図面と対応させている。結果として、各施設の提供プログラムの種類別実施状況と対応する諸室構成、ならびに精神科通所サービス施設の類型別による平面計画の傾向などを把握している。
施設により、実施プログラムに個性があり、諸室構成は多様ではあるが、複数の施設で共通するプログラムの種類とそれに対応する仕様を持つことを明らかにした。また、各施設で共通する課題も抱えていることがわかり、より効果的な治療環境を提供するための改善の余地が残されていることも示唆されている。
精神科通所施設には、居場所としての機能を求める利用者と、復職など発症前の生活にもどる訓練の場所としての機能を求める利用者の両方が存在していることも明らかにした。
この地道な研究は、利用者の疾病や通所目的に応じて柔軟な対応ができるように、一人当たりの広さに関する基準だけでなく、精神科通所施設の設計手法を生きたものにする必要な研究の一つである。
■ 研究助成金対象者
兵庫医療大学 リハビリテーション学部理学療法学科 講師 宮本 俊朗
■ 研究課題名
「神経筋電気刺激がNon-communicable Diseases関連のマイオカインに与える影響」
運動などの身体活動に代替させる神経筋電気刺激が、大腸がんなどの慢性的非感染性疾患(NCDs)の予防や、筋力・筋持久力の向上等に役割を果たすと言われるマイオカインに与える影響を、実験的に究明する基礎的研究である。
厳格なプロトコルに基づく実験と統計学的解析によって、三つのマイオカインのうち、大腸がん予防の中心と考えられるSPARCに反応が示されていることが明らかとなり、さらに十分な反応が得られなかった残り二つのマイオカインの反応についても、プロトコルと作用機序の関係を考察しつつ、対応が得られるであろうプロトコルの検証を課題にして、その分泌の可能性を展望している。
一般に電気刺激による身体への影響、殊に症状の改善、予防効果などの「効用」は広く述べられてはいるが、代謝機能を含む機序については十分に究明されておらず、推定、推論に留まっていることが多く、そのため、介入の多くは代替医療の範疇に留められている。
本研究は、今後の課題を提示しつつも、運動の行えない高齢者などに運動の代替対応を果たす科学的方法の解明に於いて核心をつく研究であり、科学的解明プロセスの一端を明らかにするものとして大きく期待されるものである。
■ 研究助成金対象者
福島県立医科大学 新医療系学部設置準備室 助手 小俣 純一
■ 研究課題名
「高電圧パルス式電流療法の新たな活用法:疼痛に対する運動療法との併用の意義の解明」
慢性疼痛を有する患者に、疼痛緩和を運動療法のみを施行した単独群とそれに加え物理療法を併用した併用群とで、効果の差を明らかにする研究である。52名の慢性疼痛患者を無作為に2群に分け、運動療法単独群と物理療法の併用群を治療開始前、治療直後、治療後1カ月の3時点において疼痛の程度、筋力、腰背部柔軟性、QOLの4項目で評価した。
併用群では治療直後、治療後1カ月後において疼痛緩和のすべての評価項目の成績が単独群より有意な改善がみられたが、治療直後と1カ月後の間では改善に有意な差がなかった。評価項目ごとの群間の比較では治療直後の疼痛の程度および腰背部の柔軟性において併用群の有意な改善が認められたが、筋力の結果については有意な差はなかった。さらに治療後1カ月ではすべての評価項目において群間の差は認められなかった。これらから物理療法の効果は有意に認められ既存の研究データとも符合しているが、治療1か月後には群間の有意な差はみられないことから、効果の持続性の面では本研究の課題としている。
運動療法を筋力維持の面のみならず疼痛緩和という側面でも評価し、そこに物理療法によるさらなる効果を探るという新しい視点と言えよう。研究結果に筋力・腰背部柔軟性・QOLについても数値化された結果を示されたい。また疼痛緩和の程度についても数値化の開発が望まれる。治療後1カ月以内にその都度併用治療を再開していけば効果を継続できるのか、など今後の発展を期待したい。
■ 研究助成金対象者
京都橘大学 健康科学部理学療法学科 助教 中野 英樹
■ 研究課題名
「パーキンソン病患者のすくみ足を改善させる指歩行運動トレーニングの開発と効果検証」
今後多くなると予想されるパーキンソン病患者の症状の中でも、患者自身が日常困っている主要な症状であるすくみ足は、改善すべき優先度の高い運動障害と考えられている。
しかしそのすくみ足を改善させるエビデンスの高い治療法が確立していないことから、新しい治療法開発の研究の重要性は高いと考えられる。
従来通りのすくみ足に対するトレーニングでは、転倒のリスクが高いこと、症状の異なるパーキンソン病患者に対して幅広くトレーニングが出来ていないことは理解することができた。
また、他の研究より明らかになっている手指タッピング課題のパフォーマンスとすくみ足の重症度との間には相関関係があることから、手指を用いた運動はパーキンソン病患者のすくみ足を改善させる可能性があると考えているが、手指を用いた運動となると解釈が広くなりすぎてしまう。
今回の研究の要となる安全で簡便なトレーニングとして出てくる指歩行運動は、まず、すくみ足と相関関係にある手指タッピング課題との関連性、あるいはそれに代わり得る活動なのかを評価、検証する必要があると思われる。また、指歩行運動自体も周知理解された運動であるとはいえず、研究を進める上においてもこの運動を用いた経緯、具体的な実施方法、評価方法の設定も必要と思われる。
研究方法ならびに研究結果、考察を踏まえて、研究①ではパーキンソン病患者における指歩行運動ならびに実歩行中の脳波活動の検討とされているが、指歩行運動、実歩行ともに、リズムに基づくことを求めたとしており、結果も考察からも、そのリズムに基づく部分の脳波の活動が増加したことはわかるものの、結論にある指歩行運動単体においては、パーキンソン病患者の実歩行と類似した脳領域を活性化されていると判断するのは難しいかもしれない。但し、今回のことで、リズムに基づいた運動であれば、同様の脳領域を活性化させることは示唆されている。
研究②の考察の部分において前頭葉のβ領域のパワー値の増減に触れているが、研究①ではその記載はない。 また、研究②の測定の条件として、間口なし条件と間口あり条件の2条件で測定し、その結果、間口なし条件では体幹加速度に有意差が出ないことからも、今回の研究対象はすくみ足ではない、あるいは病状として軽度であることが想像される。
そのことから、今回の対象者は指示した指歩行運動が問題なく遂行できた状態にあったと仮定され、指歩行運動のパフォーマンスの変化とすくみ足の状態の変化における評価が充分にできていない可能性があると考えられる。
今回、新しい治療法の開発に向けた研究目的に関しては、十分に評価できるものであったと思われる。新しい治療法として指歩行運動トレーニングの開発はまだ充分とはいえないが、引き続き研鑽を積み、社会に貢献をしていただきたいと考えている。
■ 研究助成金対象者
札幌医科大学 保健医療学部理学療法学科 理学療法学第一講座 助教 菅原 和広
■ 研究課題名
「運動による痛みの抑制と脳神経活動の関連性」
研究の目的は随意運動による脳内での疼痛をはじめとした体性感覚情報の抑制機構を調べ、随意運動による痛みの抑制機構を明らかにすることである。そのために3段階の実験を行っている。第1段階からは筋収縮後の旧新生入力は間接運動の有無の影響受けないことを明らかにしている。そこで第2、第3の実験では等調性収縮を採用している。第2実験では単純反応課題の運動練習前後における一次体性感覚野の活動を見ると反応時間の早い群と遅い群では運動練習前のP40を除いて両群で有意な差は認められなかった。第3実験では疼痛刺激にCold packを用いて、主観的な疼痛評価としてNumerical Rating Scale(NRS)を用いており、10段階(無感からこれまで感じたことのない痛みまで)で評価させている。その結果、運動の課題の難易度、筋収縮強度に関わらず持続疼痛発生時に随意運動を実施することにより、安静時と比べて持続的疼痛が減弱する結果を得ている。
既存の研究成果を踏まえて綿密な実験計画を立てて確実に実験をこなし、有益な結果を導き出しているといえよう。ただ、疼痛抑制について随意運動による脳活動と疼痛関連領域の関連性を明らかにできていないことや、主観的な疼痛の感知について客観的に示すことが残されている点を述べているが、ぜひ追研究で明らかにされたい。またリハビリテーション分野の対象者には高齢者が多いのが現実であるが、この実験は成人といっても20代の若い被験者で行われている。性別も含めて対象を広げる必要はないのか、検討されたい。既存の研究成果など全体の研究枠組みからも、脳の生理研究の一部に位置づけられるものとなる可能性がある。
■ 研究助成金対象者
山形県立保健医療大学大学院 保険医療学研究科 博士後期課程 作業療法士 花田 恵介
■ 研究課題名
「脳卒中患者における日常生活での麻痺手使用促進を目的とした包括的行動療法プログラムの開発」
本論文は脳卒中後遺症者に対して、従来のCI療法(集中的・課題指向型トレーニングと行動心理学)に上肢活動量モニタリングなどを組み合わせ、麻痺手の日常的使用について包括的介入システムを研究するものである。上肢活動量に関する適切な解析機器がみつからず、自ら計測方法を確立させている。脳卒中は寝たきり状態になる疾患とされ、救急期を脱しても障害が残るケースも多い。障害発症後の上肢機能障害は日常生活における質の低下(QOL)につながる。麻痺手の使用状態によりQOLが改善されることは、障害後の本人の人生だけでなく家族周辺の人たちの支援や負担とも大きく関わっている。そのために、本研究では上肢活動量の計測が麻痺手の回復計画に向けて重要と捉えている。生活の質は障害後の残存機能の在り様で大きく変化し、本研究で述べられているように麻痺手の可動が影響するとの考え方も肯定できる。自立した生活は、家族や周辺環境の改善に伴い自身の生活の質が向上するばかりでなく、障害をもつ本人と社会のつながりの関係性、ひいては、社会保障費の抑制に寄与する。今後は行動と心理両面からの包括的評価に向けて、加速度計の妥当性と症例を増やすことで介入効果を検証していただきたい。
■ 研究助成金対象者
帝塚山大学 現代生活学部居住空間デザイン学科 准教授 小菅 瑠香
■ 研究課題名
「全室個室病棟の使われ方に関する建築計画的研究」
「本研究は、日本では病院病棟の全室病室個室化の傾向が始まっている事に目を向け、個室化について建築計画面からその意義を明らかにして今後の病院建築設計の一助とすることを目的としたものである。研究手法は一般病院から療養病院までの27病院の全室個室病棟を対象に平面計画、5病院の現地ヒヤリング等を含めた情報を収集し、建築、看護業務、医療の質、療養の質、経営などの観点から総合的な全室個室病棟の調査を踏まえ、実際の使われ方の把握を試みている。
今回の研究結果としてまとめられている主な点は下記の通りである。
① 一床あたりの病棟面積は30㎡から45㎡に分布しており、一般病室の個室面積は15㎡前後であること。
② ベッドコントロールが容易になり転床件数が減ったこと。
③ 病床運用が柔軟に行えることにより運営次第で初期投資費用は回収できること。
④ 看守りはSSから「見える」ことより「すぐにアクセスできること」が重要であること。
⑤ 感染管理、療養環境の向上に大きな効果があったこと。
⑥ 転倒件数は同じか、自助努力による動きのため少し増える傾向があったこと。
⑦ 高齢患者の場合には食事の介助に手間がかかるためデイルームなどに集めて行いたいとの意見が多く聞かれたこと。
⑧ 観察が必要な患者の病室はSSから2スパン程度以内に配置していたこと。
⑨ 入院患者の看護必要度は平均して4日程度で変動が落ち着く傾向がみられたこと。
日本で病棟の全室個室化が見られるようになったのはここ10年ほどからであり、掘り下げた研究の対象にはなっていなかった。今回の事例研究で全室個室病棟の実態把握が進み始めたと考えるとその意義は大きい。今回はほぼ予想された内容に付け加えて新たに現場の生の声が確認できた段階である。今後は急性期、療養を含む亜急性期などの病棟でそれぞれの病棟の特徴に応じた実態調査、及び病院側の個室割り当てマネジメント手法、診療科別病棟と混合病棟の区別、個室内と多床室内で行われる診療行為の差異の有無、患者、医療スタッフ、患者家族、経営の視点等から実施することにより、更なる研究成果を期待したい。